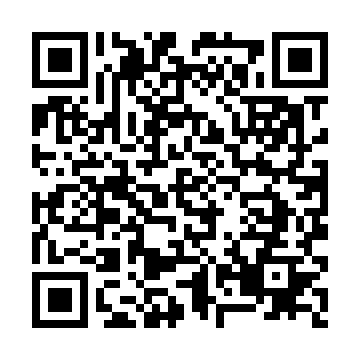秋田県内では、クマによる被害が相次いでいます。
2023年からことし2025年までの季節ごとのクマの目撃件数を見ると、ことし4~6月、つまり春から初夏にかけては1323件、7~8月の夏場は1689件となっています。どちらも2023年と2024年を大きく上回る件数です。
また、人身被害が過去最悪となった2023年は、10~12月に2100件の目撃情報が寄せられていますが、今秋は、春夏の傾向から2023年の件数を上回る可能性が指摘されています。
被害を防ぐためにどう行動すれば良いのか。県民にどのように危険を伝えるか。報道機関を対象にした研修会が開かれ、クマの生態などについて学びました。
研修会には、県内の報道機関の担当者が参加しました。
講師は、クマによる被害の分析などを担当する県自然保護課の近藤麻実さんです。近藤さんは「うっかり静かにしていて事故に遭っている。音を立てることは事故防止のために非常に大事」と事故防止の観点から注意点を説明しました。
県内では、ことし9月24日までにクマによる人身被害が13件発生し、1人が死亡、13人がけがをしています。近藤さんは「被害は3つのパターンに分けられる」と分析します。
一つ目は「防衛目的の攻撃」です。クマが自分の身や子を守るために出合った人間を襲うものです。
ことし5月、八幡平で登山をしていた40代の男性がクマに襲われた事故がこのタイプに当てはまります。男性は、親子とみられるクマに足や顔をかまれ、けがをしました。
こういった事故は、鈴やラジオなどで自分の存在を知らせることで防ぐことができ、多くの被害はこのパターンに該当します。つまり、クマに私たちの存在を知らせることが、被害を防ぐために有効な手段と言えます。
二つ目は「偶発的な衝突」です。
2023年5月、湯沢市の畑で80代の女性がクマに体当たりされ、顔にけがをしました。
このタイプの事故は、何らかの理由で走っていたクマの進路上に偶然人がいたことで発生します。偶然であるため、対策が難しいのが特徴です。
三つ目は「積極的な攻撃」です。
2022年6月、仙北市の山林で50代の女性が腕や頭をクマにかまれ、けがをしました。
これは、人が持っている食べ物を奪おうとしたり、人を食べ物と認識したりすることで発生したものと考えられています。
このような事故は、音を鳴らすなどの一般的な対策では防ぐことが難しい上に、連続して被害が起きることが多いです。そのため、この地域は入山禁止となっています。禁止された場所には決して立ち入らないようにしましょう。
日常から鈴を身に付けるなど、クマに私たちの存在を知らせるように努めることはもちろん、危険を犯すことは絶対にやめましょう。
いつでも、どこでも、誰でもクマに遭遇する恐れがあるということをしっかりと心に留めて生活することが重要です。
09月25日(木)10:00

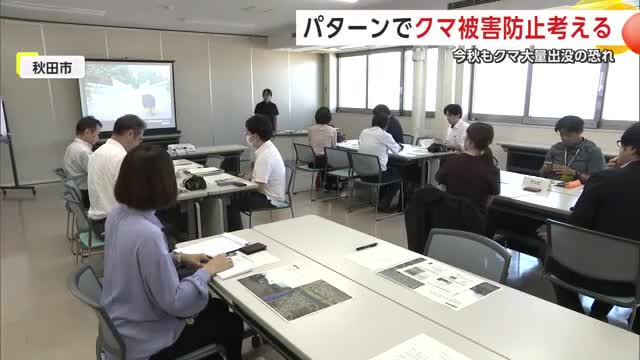 ※静止画のみ
※静止画のみ